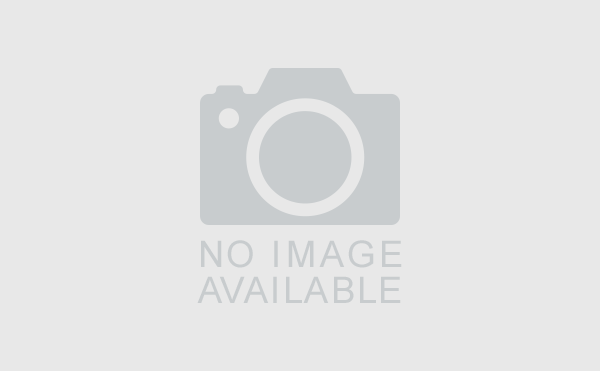北九州 永和工業|旋盤によるギア穴加工とマイクロ単位精度管理の社内教育
社内教育記事:ギア加工における旋盤技術とマイクロ単位精度管理
1. はじめに
ギアは産業機械、自動車、精密装置など、あらゆる製品の基幹部品として用いられる。その加工精度は製品の性能や耐久性に直結するため、極めて高い技術が要求される。特にギアの中心穴は組立精度や回転精度を左右する重要な部位であり、数ミクロン単位の誤差でも性能に大きく影響する。
当社では、旋盤を用いたギア穴加工において、マイクロ単位での精密加工を可能とする教育を実施している。本記事では、その教育内容と工程を紹介し、技能伝承の重要性を明らかにする。
2. 旋盤とギア加工
旋盤は円筒形状のワークを加工する工作機械であり、ギアの内径加工に広く使用される。旋盤にギアを固定し、刃物を用いて精密に穴を削り出す。このとき、単なる「削る」という作業ではなく、加工位置の正確な調整、工具の削り幅確認、測定器による精密検査を段階的に行うことで、所定の精度が達成される。
3. 教育工程(写真付き解説)
3-1. 旋盤全体像

旋盤は主軸台、往復台、刃物台などから構成される。教育の初期段階では、各部の役割を理解し、正しい取り扱いを学ぶことが重要である。誤操作は重大な事故につながるため、安全教育を徹底して行う。
3-2. ギア取り付け

ギアを旋盤に取り付ける際、芯出しの精度が最も重要である。中心が正確に合っていなければ、その後の加工はすべて無意味となる。クランプ部の清掃、適切な締め付けトルク、回転時の振れ確認を必ず実施する。
3-3. 削り位置調整

刃物をワークに近づけ、削り位置を調整する工程である。大まかな位置決めは目視で行うが、最終的には微動ハンドルを用いて数ミクロン単位の精度で合わせる必要がある。
3-4. 削り位置の最終微調整

削り開始直前の微調整では、作業者の経験値が大きく影響する。わずかなズレが仕上がり寸法に直結するため、数年にわたる訓練で正確な操作感覚を習得する必要がある。
3-5. ノギスによる削り幅確認(削る前)

削り前には、必ず工具の削り幅をノギスで確認する。これにより、刃物が正しい寸法で削れる状態であるかを事前に把握できる。ノギスの扱い方を誤ると誤差が生じやすいため注意。
3-6. バイト取り付け

下穴加工が必要な場合はドリルを使用する。バイトは旋盤加工の前処理として有効だが、軸ブレがあると仕上げ工程で補正が困難になるため、丁寧な芯出しが求められる。
3-7. 加工(削り工程)
実際の削り工程では、一度に大きく削るのではなく、複数回に分けて少しずつ寸法を近づけていく。切削音や振動から異常を察知する能力も、熟練者に求められる技術である。
3-8. 削った後のマイクロ単位測定

削り後には必ず内マイクロメーターを用いて計測を行う。穴の複数箇所を測定し、真円度や均一性も確認する。測定結果は記録し、加工履歴として残すことが求められる。測定値を次工程にフィードバックすることが精度維持の鍵である。
3-9. 内マイクロメーター

内マイクロメーターは、ミクロン単位の測定を可能とする精密測定器である。操作時に力をかけすぎると誤差が生じるため、一定の感覚で軽く当てることが求められる。教育では、この「力加減」を習得させることに重点を置いている。
3-10. 削り完了と最終確認

最終的に穴径が設計値どおりであることを確認し、品質管理表に記録する。わずかな誤差でも後工程や製品寿命に影響するため、精度を軽視しない姿勢が必要である。
4. まとめ
ギア加工における旋盤技術は、単なる機械操作ではなく、マイクロ単位の精度を追求する高度な技能である。教育を通じて若手社員がこの技術を習得することは、当社の製品力を維持し、次世代へと技術を伝える上で欠かせない。
数年にわたる訓練の先に到達できる「精密加工の世界」は、技術者としての誇りを持つに値する領域である。当社はこれからも、ギア加工教育を通じて人材育成と技能伝承を推進し、確かな品質を未来へとつないでいく。
北九州の永和工業にご相談ください。